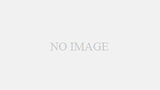- 1. 柑橘類(Citrus)キャラクターたちの世界へようこそ
- 2. 柑橘類(Citrus)のひみつをキャラクターがナビゲート
- 3. 柑橘類(Citrus)イベントに欠かせない!キャラクターの役割とは
- 4. 日本各地の柑橘類(Citrus)キャライベント事例集
- 5. 季節ごとのイベントで変わる柑橘類(Citrus)キャラの見せ場
- 6.柑橘類(Citrus)キャラグッズの人気の秘密
- 7. SNSで大人気!柑橘類(Citrus)キャラクターの発信力
- 8. 教育現場でも大活躍!柑橘類(Citrus)キャラによる食育活動
- 9. 地域活性化と柑橘類(Citrus)キャラクターの可能性
- 10. あなたの地域から発信!オリジナル柑橘類(Citrus)キャラの作り方
1. 柑橘類(Citrus)キャラクターたちの世界へようこそ
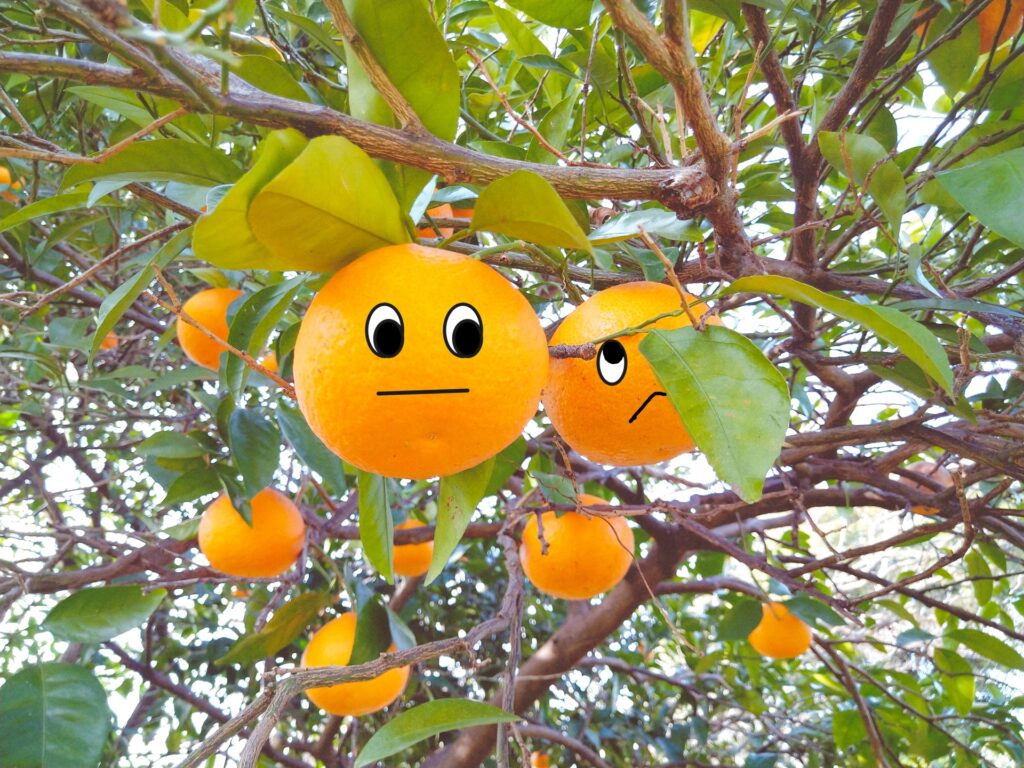
なぜ今、柑橘類(Citrus)をテーマにしたキャラクターが人気?
近年、地域の特産品や農業をテーマにした“ご当地キャラクター”の中でも、特に注目を集めているのが「柑橘キャラクター」です。ゆるキャラブームの波を超えて、今あらためて脚光を浴びている理由は、「見た目のかわいさ」だけではありません。
SNS時代において、“見てすぐにわかる”、“親しみやすい”、“地域性を感じられる”という要素が求められています。柑橘は、丸いフォルムや鮮やかな色味から、ビジュアル映えする素材として非常に優秀。また、地域ごとに育まれてきた品種の背景や、収穫の季節感、香りの個性などもキャラ設定に活かしやすく、ファンを引き寄せるポイントになっています。
さらに、環境・健康・食育といったテーマとの親和性が高い点も、教育現場や観光イベントで好まれる理由の一つです。
子どもも大人も惹きつける!柑橘類(Citrus)キャラの魅力
柑橘キャラクターが人気なのは、単に「かわいい」からではありません。子どもたちにとっては親しみやすく、食への興味を引き出す存在。大人にとっても、どこか懐かしさを感じさせる“地元の味”を象徴するアイコンとなり、SNS映えや地域応援の気持ちにつながっています。
例えば、丸くてふわふわした「みかんの妖精」や、元気いっぱいの「ゆずヒーロー」など、キャラごとに設定される個性は、ブランド化の起点にもなっています。地域PR動画やLINEスタンプ、グッズ展開など、活用の幅が広がっているのも見逃せません。
また、柑橘には“家族団らん”や“冬のこたつ”など、日本人にとって心あたたまるイメージが多く結びついています。そのイメージとキャラクターがリンクすることで、自然と好感度の高い存在になるのです。
キャラを通して学べる「食育」や「健康」の大切さ
柑橘キャラクターの持つ“学びの力”も大きな魅力です。子どもたちは、みかん型のキャラが登場する絵本やアニメーションを通じて、「旬ってなに?」「ビタミンCってどんな栄養?」といった疑問を自然に抱きます。
たとえば、柑橘キャラが風邪をひいた友だちにビタミンを届ける…そんなストーリーを通じて、食と健康の関係を楽しく伝えることができます。これは、管理栄養士監修のキャラ教材などでも多く活用されており、単なるエンタメにとどまらない“教育メディア”としての価値を持っています。
また、近年は「アレルギーに配慮した柑橘レシピをキャラが紹介する」といったコンテンツや、「旬の柑橘を使った献立を学校給食と連動して紹介する」取り組みも進んでおり、家庭と地域をつなぐ存在としての役割も期待されています。
2. 柑橘類(Citrus)のひみつをキャラクターがナビゲート

みかんだけじゃない!世界のシトラス紹介
「柑橘って、みかんとオレンジくらいじゃないの?」と思っていませんか? そんな常識をくつがえすのが、柑橘キャラクターたちの最大の仕事。「こんにちは!ぼくはシトラス博士レモンくん!」というように、子どもたちにフレンドリーに語りかけながら、彼らは世界中の柑橘たちを楽しく紹介してくれます。
実際、柑橘は世界に1,000種以上存在するといわれており、味も形も千差万別。日本では温州みかんやはっさく、ポンカンなどが親しまれていますが、世界にはユズ、ベルガモット、ブラッドオレンジ、タンジェリン、カラマンシーなど、まだまだ知られていないシトラスがたくさんあります。
キャラクターたちが“旅する”ストーリーにして紹介すれば、子どもも大人も、いつの間にかシトラス博士になれるかも?
柑橘類(Citrus)キャラ図鑑:産地別の代表キャラたち
柑橘キャラクターは、それぞれの産地で“地域代表”として活躍しています。たとえば和歌山県の「ありだん」は有田みかんをイメージした元気いっぱいのキャラ、愛媛の「せとか姫」は高級柑橘せとかをモチーフにしたお姫様風のキャラクターとして観光客に大人気。
静岡の「みかっぴー」や、鹿児島の「ボンタンマン」など、地元愛にあふれた名前やデザインも親しみやすさの秘訣です。キャラごとにバックストーリーがあり、たとえば「デコポンのかぶりものをしている理由は…?」など、謎解き感覚で読み進められるキャラ図鑑は、食育教材や観光パンフレットとしても大活躍しています。
こうしたキャラクターを入り口に、子どもたちは“地元の特産品”に誇りを持つようになりますし、大人たちにとっても「これはあの土地の○○だね」と、地域の知識が自然に深まるきっかけになります。
香り・味・色で分類する柑橘類(Citrus)の世界
キャラクターたちは、柑橘の奥深い魅力もわかりやすく教えてくれます。たとえば、レモンくんは「香り担当」、グレープフルーツちゃんは「色担当」、甘夏のおじいちゃんは「味担当」など、役割分担しながら柑橘の個性をナビゲート。
・香り:ユズやカボス、すだちは香りが強く、アロマや香水、調味料にも使われます。
・味:酸味の効いたレモン系から、まるでスイーツのように甘いせとかや紅まどんなまで、味わいの幅が魅力です。
・色:オレンジ色が多いと思われがちですが、ルビーグレープフルーツの赤、ニューサマーオレンジのクリーム色など、彩りも多様。
キャラクターたちが「今日のテーマは“黄色の仲間たち”!」といった具合に紹介することで、食育だけでなく、色彩や味覚に対する感性も自然と育まれます。
3. 柑橘類(Citrus)イベントに欠かせない!キャラクターの役割とは

柑橘イベントの現場に欠かせない存在、それが柑橘をモチーフにしたキャラクターたちです。近年では、地域のシンボルやマスコットキャラとして活躍するだけでなく、イベントの運営やPRの中核を担う“顔”としてその役割がますます大きくなっています。
地域のマスコットからPR大使へ
もともと各地域に根ざした柑橘キャラクターは、「みかん丸」や「ゆず吉」など、親しみやすいネーミングとビジュアルで、地元の子どもたちに愛されてきました。最近では、その活躍の場が広がり、行政や観光協会と連携してイベントPRや特産品の販促にも起用されています。SNSやWebサイトの顔として登場したり、テレビCMに出演したりするなど、まさに“PR大使”としての存在感を放っています。
イベント会場を盛り上げる!キャラクターショーの裏側
柑橘キャラが主役を張るのが、イベント当日の「キャラクターショー」です。子どもたちが大喜びするミニ劇やクイズ大会、ダンスパフォーマンスなどは、会場を盛り上げる重要なコンテンツ。キャラの“中の人”は地域のボランティアやスタッフであることも多く、台本や演出は手作り。だからこそ、観客との距離感が近く、心のこもった温かいステージが生まれるのです。
「会える」楽しみが広がる、リアル&バーチャル出演
近年は、リアルイベントに加えてオンラインでのキャラクター活用も進化しています。たとえば、Zoom配信でキャラクターと一緒にジュースを作る体験や、メタバース空間で開催される「バーチャル柑橘収穫祭」など、参加のハードルが下がる工夫が増えています。SNSのライブ配信で「今日は○○県のイベントに行ってきたよ!」と報告するキャラクター投稿は、ファンの共感と拡散を呼び、イベントの告知にもつながっています。
4. 日本各地の柑橘類(Citrus)キャライベント事例集

柑橘をモチーフにしたキャラクターたちは、今や地域イベントの主役級の存在です。とくに柑橘の名産地では、独自のご当地キャラが登場し、イベントに彩りとにぎわいを添えています。ここでは、日本各地で実際に行われている柑橘キャラクター関連のイベントをいくつかご紹介します。
和歌山「みかんヒーローショー」
みかんの生産量全国トップを誇る和歌山県では、「みかん戦隊アリダンジャー」というヒーローキャラが地元イベントで活躍中。毎年秋に開催される「有田みかん祭り」では、子ども向けのヒーローショーが大人気。みかんを守るために悪の農薬怪人と戦うストーリーには、環境保全や農業の大切さを伝えるメッセージも込められており、楽しみながら学べる内容となっています。
愛媛「かんきつ王国フェス」のキャラ企画
「みかん県」とも呼ばれる愛媛県では、冬に開催される「かんきつ王国フェス」でご当地キャラが大集合します。なかでも注目は、「みきゃん」とそのおともだちキャラ「ダークみきゃん」「こみきゃん」。フォトセッションやミニパレード、子ども向けのクイズ大会など、来場者と一緒に楽しめるコンテンツが盛りだくさん。SNS上でも「#みきゃんに会えた」が多数投稿され、フェスの拡散力に一役買っています。
静岡「三ケ日みかんまつり」とキャラクターパレード
静岡県浜松市では、ブランドみかん「三ケ日みかん」の収穫シーズンに合わせて「三ケ日みかんまつり」が開催されます。このイベントの見どころは、「ミカちゃん」と名付けられた三ケ日みかんの妖精キャラによるパレード。地域の保育園や小学校と連携し、子どもたちが手作りした“ミカちゃん帽子”をかぶって一緒に練り歩く参加型イベントとして人気を集めています。
5. 季節ごとのイベントで変わる柑橘類(Citrus)キャラの見せ場

柑橘キャラクターたちの魅力は、その可愛さや親しみやすさだけではありません。彼らが活躍するイベントの“見せ場”は、季節ごとにしっかりと変化し、柑橘の旬や地域の風土と見事にリンクしています。ここでは、春夏秋冬それぞれでどんな「キャラの見せ場」があるのかをご紹介しましょう。
冬の収穫祭とあったかコスチューム
冬はまさに柑橘の季節。温州みかんをはじめ、伊予柑やデコポンなど多くの柑橘が旬を迎える時期です。各地で開催される「みかん収穫祭」や「柑橘フェス」では、キャラクターたちがあったか仕様の冬コスチュームで登場!手袋やマフラー、毛糸の帽子などをまとった姿は、子どもから大人まで思わず笑顔になる可愛らしさです。
また、雪が降る地域では「雪とみかん」をテーマにしたイベントもあり、柑橘キャラがスノーシューズ姿で雪遊びを楽しむ演出も。屋外の果樹園でも寒さを吹き飛ばすように、キャラたちが手を振って元気いっぱいに盛り上げます。
春の花咲く柑橘類(Citrus)園でのキャラ撮影会
3月〜5月にかけては、柑橘の花が咲き誇る爽やかな季節。この時期には、柑橘園を舞台にした「撮影会イベント」が増えてきます。柑橘キャラたちは、花の香り漂う果樹園を背景に、春らしいパステルカラーの衣装で登場。自然光と新緑に包まれて、SNS映えする写真がたくさん撮れることから、若年層や家族連れにとても人気です。
中には、来場者のスマホでキャラがポーズをとってくれる「フォトサービス付き撮影会」や、「キャラスタンプラリー」との連動企画など、エンタメ性を高めたイベントも開催されています。
夏のジュース体験とひんやりグッズとのコラボ
夏は柑橘の収穫量こそ少ないものの、ジュースやシャーベットといった加工品が主役になる季節。柑橘キャラたちは、冷たいドリンクをPRする“涼しげ衣装”で登場します。麦わら帽子、アロハシャツ、氷をイメージしたデザインなど、季節感満載の姿が夏の暑さを和らげてくれます。
とくに人気なのが「ジュースづくり体験」のサポート役としての登場。柑橘キャラと一緒に果汁を絞ったり、オリジナルラベルを貼ったりと、思い出に残る夏イベントに。さらに、キャラクターのイラスト入りの保冷バッグや冷感タオルなど、ひんやりグッズとのコラボ商品も続々登場し、イベントの“お土産需要”にも貢献しています。
6.柑橘類(Citrus)キャラグッズの人気の秘密

柑橘キャラクターの魅力は、その愛らしいビジュアルや親しみやすいストーリー性にとどまりません。イベントやSNSなどでの露出を通して育まれた“ファン層”に向けたグッズ展開が、今大きな注目を集めています。ここでは、そんな柑橘キャラグッズの人気の理由を、具体的な事例とともにひもといていきます。
地域限定アイテムと通販戦略
まず注目すべきは、「地域限定」という付加価値です。たとえば、和歌山県の柑橘ヒーロー「ミカンマン」は、有田限定のトートバッグや缶バッジを販売しており、「現地でしか手に入らない」という希少性がコレクター心をくすぐります。こうしたグッズは道の駅や観光案内所、農園の直売所で取り扱われることが多く、来場の“お楽しみ要素”として機能しています。
一方で、最近では地域のECサイトやふるさと納税返礼品としてオンライン展開も進んでおり、遠方のファンでも手に入りやすくなっているのも人気の理由です。オリジナルステッカーやLINEスタンプなど、デジタル商品も展開することで、より多様なファン層へアプローチできています。
食べられる!? キャラクター付きスイーツ&ドリンク
柑橘キャラの強みは“食品との親和性”が高い点にもあります。イベント会場や道の駅では、キャラクターをモチーフにした「焼き印入りどら焼き」「プリントクッキー」「みかん風味マカロン」など、思わず写真を撮りたくなるスイーツが登場。
さらに、柑橘ジュースのパッケージにキャラクターを採用することで、「かわいいから買いたくなる」という“見た目買い”需要にも対応。子どもがパッケージを見て「これがいい!」と選ぶことで、自然と柑橘の摂取機会が増えるという“食育効果”も期待できます。
中には、農園とコラボして「キャラオリジナルみかんジュース」を開発する地域もあり、味の違いだけでなくパッケージデザインを変えることでリピーターを増やす工夫も見られます。
子どもに人気!シール・ぬりえ・ぬいぐるみ展開
お子さま向けグッズとして圧倒的人気を誇るのが、シールやぬりえ、ぬいぐるみといった“遊び要素”を含んだアイテムです。特にイベントでは、「キャラクターシールラリー」や「ぬりえコンテスト」などと連動することで、来場者の滞在時間や満足度がアップします。
ぬいぐるみは定番中の定番ですが、地域の素材を使った手作りタイプや、地元の福祉施設と連携した製作によって、「ストーリー性+社会貢献」が加わることでファンの愛着もより深まります。
また、近年では紙製グッズの人気も上昇中。環境配慮型の素材を使った「エコペーパーシール」や「再生紙メモ帳」は、柑橘の自然イメージとも相性がよく、エシカルな視点を持つ若年層にも評価されています。
柑橘キャラグッズは、見た目の可愛らしさや遊び心だけでなく、地域の魅力や産品の味わいを“持ち帰れる”形で表現する大切なツールです。今後は、よりインタラクティブな仕掛けやサステナブルな素材との融合も期待されており、「グッズ=コミュニケーションメディア」としての役割を強めていくことでしょう。
7. SNSで大人気!柑橘類(Citrus)キャラクターの発信力
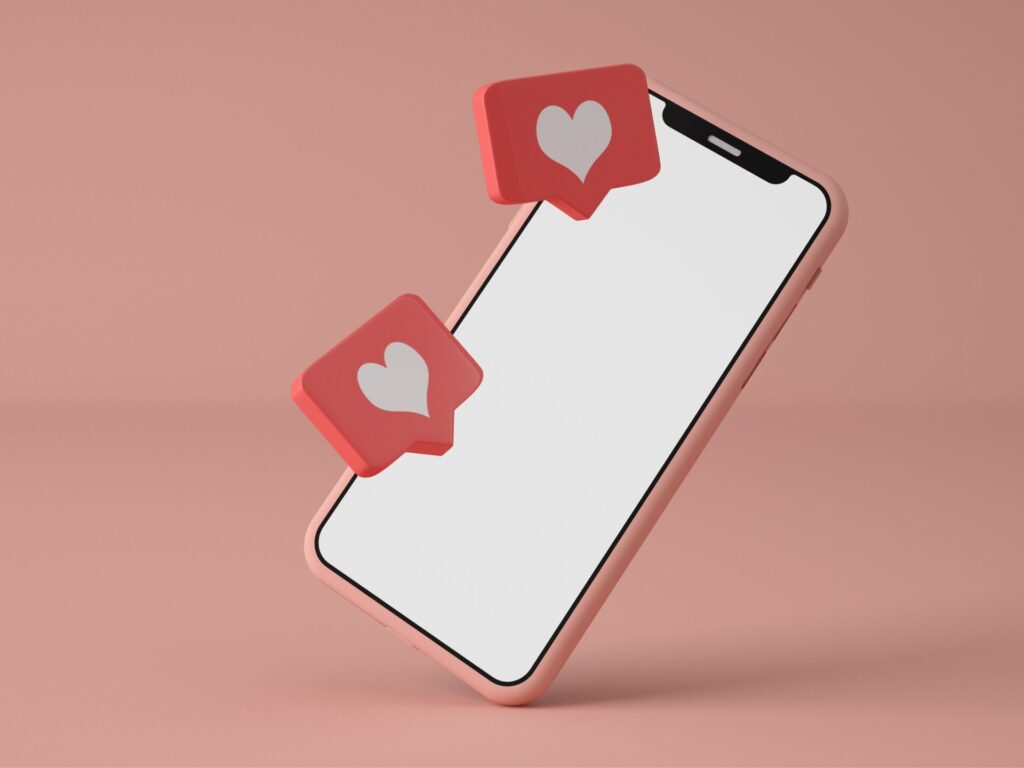
柑橘キャラクターは、今や「現場」だけでなく「画面越し」でもファンを魅了する存在へと進化しています。特にSNS(Instagram、X〈旧Twitter〉、TikTokなど)との相性は抜群で、親しみやすさ・季節感・健康イメージを活かした発信で多くの支持を集めています。この章では、SNSにおける柑橘キャラの活躍と、拡散を加速させる発信術に迫ります。
フォロワー1万人超えのご当地キャラアカウント紹介
たとえば、愛媛県の「みきゃん」は、X(旧Twitter)やInstagramで全国にファンを持つご当地キャラクター。季節ごとのイベント告知や、柑橘の豆知識、ゆるい日常投稿が絶妙にミックスされた運用で、フォロワー数は常に右肩上がり。柑橘を使ったレシピや地域の特産紹介を“キャラの目線”で投稿することで、地域情報の発信にもなっています。
同様に、和歌山の「かんきつ戦隊ミカンジャー」や、静岡の「みかん王子」など、地域を背負った柑橘キャラたちが、それぞれの「声」で日々ファンとつながりを深めています。
イベントとの連動で拡散力アップ
リアルイベントとSNS発信を連動させることで、相乗効果が生まれます。たとえばイベント前には「○○で会えるよ!」という予告投稿、当日は写真やライブ配信で現地の雰囲気を伝え、イベント終了後には「ありがとう投稿」で感謝を伝える。こうした一連の流れにより、イベント参加者とのつながりがより深まり、次回の集客にもつながります。
特に有効なのが、来場者が自ら投稿したくなる“仕掛け”づくり。会場内にSNS映えするフォトブースを設置したり、指定のハッシュタグ投稿で限定グッズがもらえるキャンペーンを実施することで、自然な形でSNS拡散が起こります。
ハッシュタグ活用術とユーザー投稿事例
柑橘キャラを使ったSNS運用で欠かせないのが、ハッシュタグの戦略的な活用です。たとえば…
- #みかんキャラ
- #かんきつイベント
- #○○(地域名)ゆるキャラ
- #ご当地フルーツ
- #柑橘と暮らす
など、目的別に複数のハッシュタグを併用することで、検索性と拡散力が格段にアップします。
また、一般ユーザーによる投稿もコンテンツ資産になります。子どもとキャラが撮った写真、キャラクターグッズの感想、みかんレシピとのコラボ投稿など、ファンによる「自発的な発信」が、ブランドの信頼性や親しみやすさを広げてくれるのです。
公式アカウントがそれらを「いいね」や「リポスト」することで、ファンとの双方向コミュニケーションが生まれ、「私の投稿が紹介された!」という体験がさらなるファン化につながります。
8. 教育現場でも大活躍!柑橘類(Citrus)キャラによる食育活動

近年、教育現場でも「柑橘キャラクター」が食育のパートナーとして注目されています。栄養や健康に関する知識を小さな子どもたちに伝えるには、楽しさや親しみやすさが欠かせません。その点、柑橘キャラはビジュアルの可愛さや地域色の濃さに加え、「果物=健康的」というイメージが強く、教育現場と非常に相性が良いのです。
幼稚園・保育園での訪問イベント
保育園や幼稚園では、柑橘キャラクターによる「訪問イベント」が増えています。キャラが園を訪れ、子どもたちと一緒に体操をしたり、柑橘にまつわる紙芝居を読み聞かせたり、手洗いの大切さや旬の果物の美味しさを伝えることで、子どもたちの関心を引き出します。
たとえば、愛媛の「みきゃん」がみかんの栄養や産地の話をする“お話会”では、普段野菜や果物が苦手な子でも「食べてみようかな」と思えるきっかけになるとの声も。楽しい体験を通じて自然に「食べることの大切さ」を学べるのがポイントです。
キャラ絵本・動画で学ぶ「旬」や「栄養」
最近では、柑橘キャラクターを主人公にした絵本やアニメ動画も制作されており、学校や家庭での食育教材として活用されています。
たとえば「ミカンぼうやの季節めぐり」シリーズでは、ミカンぼうやが日本各地の果樹園を旅しながら、旬の時期、栽培の工夫、そして自分の体に良いことを楽しく学べる構成になっています。アニメーションで果物の成長過程を紹介する動画も、視覚的に理解しやすく、小学校低学年にも好評です。
また、キャラクターを活用した「旬のカレンダー」や「色と味で覚える柑橘図鑑」など、視覚的な教材も充実してきており、食の授業に新たなアプローチを加えています。
学校給食や授業で使われるキャラクター教材
柑橘キャラクターは、学校給食にも登場しています。地元の旬の柑橘が給食に出される日には、キャラが印刷された「食育カード」や「おいしさのひみつポスター」が配られ、子どもたちに果物の魅力を伝えます。
一部の学校では、キャラクターを使った特別授業も実施されており、栄養士が登壇して「ビタミンCがなぜ必要か」「皮の香り成分リモネンの効果」などを紹介する時間が設けられることも。キャラを通して、普段の食事や生活習慣に関心を持ってもらえる機会となっています。
柑橘キャラクターは、教育現場に“学びと楽しさ”を両立させる存在として、今後さらに重要な役割を担っていくでしょう。子どもたちの心に届く“柑橘の先生”として、全国で活躍の場を広げています。
9. 地域活性化と柑橘類(Citrus)キャラクターの可能性

柑橘をテーマにしたキャラクターは、ただ可愛らしいだけではありません。地域の文化や農業、観光を結びつける“顔”として、今や地域活性化のキーパーソンとなっています。特に、農業のブランド力強化、若年層や親子層へのアプローチ、そして6次産業化との連携によって、柑橘キャラクターの存在価値は年々高まってきています。
キャラが変える!農業のブランディング
農業の世界では、長年続けられてきた品種や栽培方法に注目を集めることが難しくなってきました。そこで登場したのが、柑橘キャラクターたち。たとえば和歌山の「キュンちゃん」や、愛媛の「みきゃん」など、地元の特産品を背負ったキャラは、地域を象徴する“農のブランドアイコン”としての役割を果たしています。
キャラを活用したロゴやパッケージデザインは、道の駅やネット販売でも目を引きやすく、初めて訪れる観光客や若い世代の購買意欲を高めるきっかけに。キャラクターが前面に出ることで、消費者が地域産の柑橘に愛着を持ち、リピート購入につながるケースも多く報告されています。
若者・親子層へのアプローチ強化事例
従来の農業イベントは高齢者や地元住民が中心でしたが、柑橘キャラクターを取り入れることで、若い親子連れや都市部からの観光客にもぐっと間口が広がりました。
たとえば、静岡県の「三ケ日みかんまつり」では、キャラクターショーと同時に収穫体験やジュース作り体験が開催され、週末には家族連れで大賑わい。キャラと一緒に写真を撮った子どもたちの投稿がSNSで拡散されることで、イベント自体の認知度も急上昇しました。
また、地元高校の生徒がキャラクターと連携して開発した「柑橘ドリンク」や「スイーツ」の販売など、若者のアイデアと柑橘キャラを掛け合わせた取り組みも増えています。
キャラを中心に据えた6次産業化の実例
農業の6次産業化(生産・加工・販売の一体化)においても、柑橘キャラクターは強力なアクセントとして活躍しています。たとえば、地元の柑橘を使ったマーマレードやゼリー、ドリンクなどの加工品にキャラをデザインとして載せることで、商品価値が高まり、土産物としての魅力もアップ。
さらに、イベント会場でキャラクターが登場することで、その場での購買意欲が高まり、試食→購入→SNS投稿という“連鎖”を生み出しています。これはまさに、体験が商品に付加価値を与える6次産業化の成功モデルといえるでしょう。
地域の魅力を再発見し、新たなファンを生み出す“柑橘キャラクター”。その活躍は、もはや農業や観光の枠を越え、地域社会全体をつなぐキーパーソンになりつつあります。
10. あなたの地域から発信!オリジナル柑橘類(Citrus)キャラの作り方

「うちの地域にも柑橘キャラがいたらいいのに…」そう思ったことはありませんか?じつは、特別な資金や専門知識がなくても、地元の特色や人々の思いを活かして、素敵なオリジナルキャラクターは生み出せます。地域に愛され、長く育てていける柑橘キャラクターを作るためのステップとアイデアをご紹介します。
ストーリー・名前・デザインの考え方
まず大切なのは、キャラクターに込める“物語”です。たとえば、「温暖な土地で太陽と海風を浴びて育った」「人間の健康を守るために柑橘の妖精として現れた」など、地域の気候や歴史、柑橘の個性を活かしたストーリーが、キャラに深みと説得力を持たせてくれます。
名前も重要な要素です。地元の方言や地名、柑橘の品種名を組み合わせることで、愛着が湧くネーミングが可能です。たとえば「はるみん」「ゆずのすけ」「せとまる」などは、品種×親しみのある語尾で覚えやすさも抜群。
デザインでは、地域の子どもや学生のアイデアを取り入れるのもおすすめ。ゆるキャラ風、アニメ風、動物モチーフなど、親しみやすい見た目にすることで、幅広い年齢層に受け入れられます。
地元住民と一緒に育てるキャラクター戦略
キャラクターは「作って終わり」ではありません。地域の人たちが一緒に“育てていく”ことで、愛され、長く支持される存在になります。
そのためには、まずは小さな活動から始めるのがポイントです。地域の直売所でキャラが描かれたポップを置いたり、SNSで旬の柑橘やレシピをキャラ目線で発信したり。学校や保育園とのコラボで「ぬりえ」「着ぐるみ登場イベント」を行うのも効果的です。
また、町内会や商工会、観光協会との連携も欠かせません。地元メディアに取り上げてもらったり、スタンプラリーのマスコットに起用したりと、露出の場を広げる工夫を重ねていくことがカギです。
イベントデビューまでのスケジュールとヒント
キャラクターをお披露目するなら、「イベントでのデビュー」が一番効果的です。地元の収穫祭やマルシェ、道の駅の記念日など、人が集まる機会に登場させましょう。以下は、一般的なスケジュールの例です:
- 1~2か月目: アイデア出し、ストーリー&デザインの決定
- 3か月目: 名前の公募・決定、ロゴやポスターの制作
- 4か月目: 地域メディア・SNSでプレ告知
- 5か月目: デビューイベント開催(着ぐるみやフォトスポットなど)
キャラクターが登場することで、地域の柑橘そのものにも注目が集まり、ブランド力や販売力の向上にもつながります。
柑橘キャラクターは、地域の魅力を“人の心に届くかたち”で伝える力を持っています。あなたの街から生まれる新たなスターが、地元の農業・観光・暮らしを元気にする第一歩になるかもしれません。