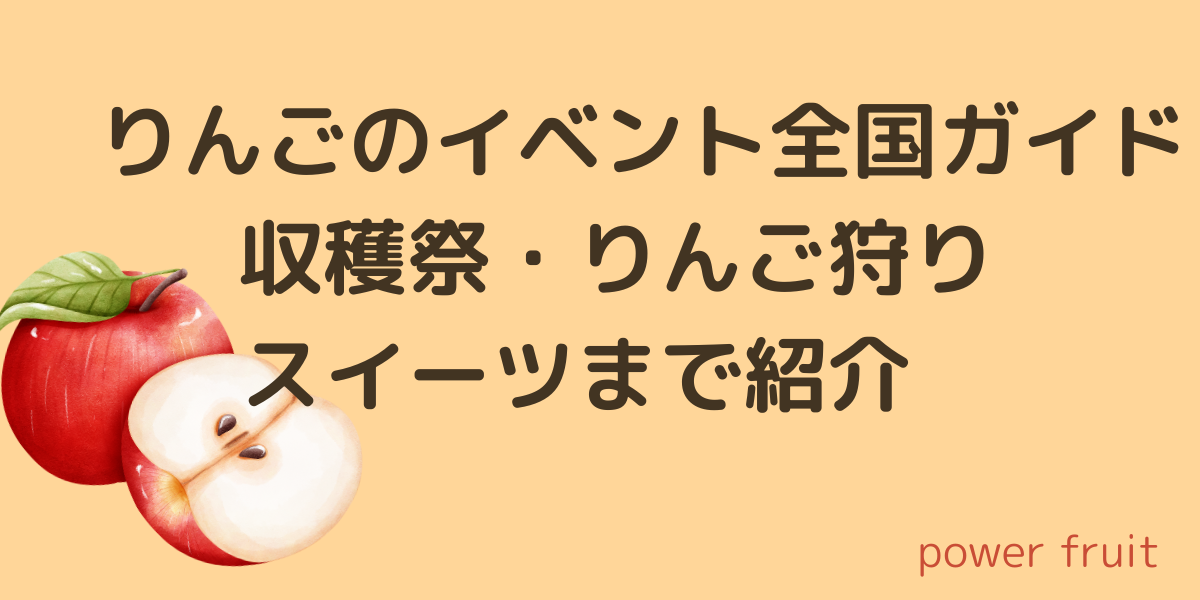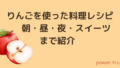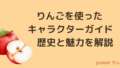りんご(林檎/apple)は、日本各地で秋の実りを祝うシンボルとして親しまれています。青森や長野をはじめ、全国では収穫祭やりんご狩り、スイーツフェスやシードルイベントなど、多彩な企画が開催されます。
本記事では、旬の時期に行われる主要イベントを中心に、家族で楽しめる体験や地域とのつながり方を紹介します。
▼ りんごに関する最新情報や関連コラムはこちら
- 1. りんごの季節を楽しむはじまり ― 全国で盛り上がるりんごイベントの魅力
- 2. りんご狩り体験 ― 味わうだけでなく収穫の喜びを感じる
- 3. 地域ブランドを支える「りんご祭り」 ― 産地の誇りとにぎわい
- 4. りんごスイーツフェス ― おいしさと創造性の競演
- 5. りんごと音楽・アートの融合イベント ― 五感で味わう新体験
- 6. りんご農家と出会う ― 作り手の想いを伝える交流イベント
- 7. シードルフェスティバル ― 発酵文化と地域の再発見
- 8. りんごでつながる家族イベント ― 親子で学び楽しむ企画
- 9. オンライン・デジタル時代のりんごイベント ― 新たな発信の形
- 10. 未来へ実るりんごイベント ― 地域・人・文化をつなぐ架け橋
1. りんごの季節を楽しむはじまり ― 全国で盛り上がるりんごイベントの魅力

日本各地では、秋の訪れとともにりんごの収穫を祝うイベントが開催されます。青森・長野・山形をはじめとする主要産地では、地元の生産者や観光客が一体となり、収穫の喜びを分かち合う季節の風物詩となっています。りんごを味わうだけでなく、地域の文化や人とのつながりを感じられるのが大きな魅力です。
青森県・弘前りんご花まつりから始まる季節のサイクル
りんごの一大産地・青森県では、開花期の5月に「弘前りんご花まつり」が開催されます。りんごの花が満開を迎える時期に、弘前公園のりんご園ではライトアップや写真コンテストなどが行われ、春から秋への季節の移り変わりを告げる行事として親しまれています。花まつりは、単なる観光イベントではなく、りんご産業に携わる人々が自然の恵みに感謝する機会でもあります。農家が交わす「今年も良い実りを」という言葉に、産地の誇りと期待が込められています。
秋の主役「りんご収穫祭」 ― 食と体験が楽しめる旬のイベント
収穫シーズンの9月〜11月にかけては、全国各地で「りんご収穫祭」や「りんごフェスティバル」が開催されます。青森県弘前市の「弘前りんご収穫祭」、長野県の「信州りんご三昧フェスタ」などでは、収穫体験や直売、りんごスイーツの販売が行われ、家族連れや観光客でにぎわいます。りんごの品種食べ比べコーナーやシードル試飲会も人気で、消費者が生産者の想いを直接知る貴重な機会となっています。また、地方の小規模イベントでも、地元学生の音楽演奏やフードトラックが加わり、地域全体がひとつの「りんごのまち」として盛り上がるのが特徴です。
地域をつなぐ「りんごフェス」 ― 持続可能な農業への取り組み
近年では、りんごイベントが地域の観光振興だけでなく、持続可能な農業や地域活性化の場としても注目されています。たとえば青森県板柳町で行われる「りんごまるかじりまつり」では、環境にやさしい農法や6次産業化の取り組みを紹介するブースが並びます。また、長野県ではエコ農業に取り組む若手生産者が中心となり、規格外りんごを活用したスイーツや加工品を販売するなど、フードロス削減をテーマとした企画も増えています。りんごの魅力を食だけでなく社会的な価値として伝える動きが広がっており、こうしたイベントが次世代の農業や地域づくりを支える大きな力となっています。
2. りんご狩り体験 ― 味わうだけでなく収穫の喜びを感じる

りんご狩りは、秋の味覚を代表する人気の体験型イベントです。青森・長野・山形・秋田などの産地では、観光農園が一般開放され、もぎたてのりんごを味わいながら自然や農業の魅力を感じられます。家族旅行や食育の一環としても注目されており、日本の秋の風物詩として多くの人に親しまれています。
【関連リンク】▶りんごをそのまま食べるおすすめの方法
各地の人気スポットと旬の時期
りんご狩りのベストシーズンは、地域によって少しずつ異なります。青森県では9月下旬から11月上旬、長野県では10月前後が最盛期です。青森市の「弘前りんご公園」では約80種、2,300本のりんごの木が栽培されており、人気の「ふじ」や「王林」などを自分の手で収穫できます。長野県中野市や須坂市の観光農園では、標高の違いによって収穫時期がずれるため、長くりんご狩りを楽しめるのが魅力です。また、山形県の朝日町や福島県の会津地方など、近年は東北全体で観光農園の整備が進み、県をまたいで楽しむ旅行プランも人気を集めています。
りんご狩りの魅力 ― 味・香り・音まで楽しむ体験
りんご狩りの魅力は、ただ食べるだけではありません。自分の手で枝を引き寄せ、りんごをくるりとひねってもぐ感覚や、収穫した瞬間に広がる甘い香りも体験の一部です。もぎたてのりんごは水分を多く含み、シャキッとした歯ごたえと爽やかな酸味が特徴。農園によっては、品種別の味の違いを説明してくれるガイドがつくところもあり、「同じふじでも畑によって香りが違う」など、食べ比べを通して新たな発見ができます。また、園内ではりんごジュースの搾り体験やアップルパイづくりのワークショップが開催されることもあり、子どもから大人まで幅広く楽しめます。
家族で楽しむ秋の思い出づくり
りんご狩りは、家族の秋のレジャーとしても人気です。多くの観光農園では、ベビーカーでも入れる平坦な通路や、休憩用の東屋、キッズスペースを設けるなど、小さな子ども連れでも安心して参加できる工夫がされています。収穫後には、その場で撮影できる「フォトスポット」や、地元野菜やシードルなどが並ぶ直売所も併設され、家族でゆっくり過ごせる環境が整っています。りんごを通じて自然とふれあい、季節の移ろいを感じる体験は、都市部ではなかなか得られない貴重な時間です。農家との交流を通して「食のありがたさ」を知るきっかけにもなり、観光と教育の両面から人気が高まっています。
3. 地域ブランドを支える「りんご祭り」 ― 産地の誇りとにぎわい

日本各地で秋になると開かれる「りんご祭り」は、地域の特産品としての誇りを伝え、農家・観光客・地元住民が一体となって盛り上がる重要なイベントです。単なる販売会ではなく、地域文化や食育、観光を結びつける「まちづくり」の一環としても注目されています。
弘前りんご収穫祭 ― 日本一の産地が誇る伝統イベント
青森県弘前市で毎年10月に開催される「弘前りんご収穫祭」は、日本有数のりんご産地が誇る大規模イベントです。弘前市りんご公園を会場に、約2,300本のりんごの木を背景に開かれるこの祭りでは、収穫体験、りんご品評会、シードル試飲、特産品販売など多彩な催しが行われます。中でも注目を集めるのが「巨大アップルパイ焼き実演」。直径2メートルを超える鉄板で焼き上げられる光景は迫力満点で、地元学生や観光客が一緒に楽しむ恒例行事となっています。また、弘前市内の洋菓子店が共同開発した限定スイーツも人気で、「りんごのまち弘前」を象徴するイベントとして毎年多くの来場者が訪れます。
長野りんごまつり ― 信州の豊かな風土を感じる催し
長野県でも、各地で地域に根付いたりんご祭りが開かれています。中でも「信州中野りんごまつり」や「須坂りんごフェスタ」は、地元生産者が自慢のりんごを持ち寄り、試食販売や直送予約ができるイベントとして人気です。信州りんごは標高差による寒暖の差と日照時間の長さから、糖度が高く香り豊かな味わいが特徴。イベントではその年の出来を比べながら、農家と直接話せるのも魅力です。ほかにも、りんごを使ったカクテルやシードルの提供、信州産チーズとのペアリング体験など、地元の食文化を生かしたコンテンツが充実しています。観光だけでなく、食の学びの場としても評価されています。
山形・秋田のまちぐるみイベント ― 人と人をつなぐ地域交流
東北地方では、りんごを通じた地域交流型のイベントも盛んです。山形県朝日町では「朝日町りんごまつり」が毎年11月に行われ、規格外りんごをお得に販売する「詰め放題」が大人気。地元高校生による音楽演奏や、りんごスイーツコンテストも開催され、町全体がにぎわいを見せます。秋田県横手市の「よこてりんごまつり」では、地域のりんごブランドサンふじや秋田紅あかりをPRするブースが並び、農家と消費者の交流が活発に行われています。これらのイベントは単なる物産販売にとどまらず、「地元のりんごを食べて地域を応援しよう」というメッセージを発信しており、地域経済や観光振興の原動力にもなっています。
4. りんごスイーツフェス ― おいしさと創造性の競演

りんごをテーマにしたスイーツイベントは、全国で注目を集めています。産地の新鮮なりんごを使ったパティスリーの限定メニューや、地元学生・職人による創作スイーツが並び、味覚と見た目の両方で楽しめる秋の恒例行事です。地域の特産を新しい形で発信する場として、観光客だけでなくメディアからも関心を集めています。
青森・弘前アップルパイまつり ― りんごスイーツの聖地
りんごスイーツを語るうえで欠かせないのが、青森県弘前市で行われる「弘前アップルパイまつり」です。弘前はアップルパイのまちとして知られ、市内には50軒以上のアップルパイ専門店やカフェが点在します。イベントでは、それぞれの店が個性豊かなアップルパイを販売し、観光客が食べ比べスタンプラリーでお気に入りの一品を探すのが人気です。パイ生地の食感や使用する品種(紅玉・ふじ・王林など)によって味わいが異なり、「弘前りんご」の多様性を楽しむことができます。観光と食の両面で地域の魅力を発信する好例であり、地元高校生によるアップルスイーツ開発など、若い世代の参加も増えています。
信州・りんごスイーツフェア ― パティシエと農家のコラボレーション
長野県では、県内の洋菓子店が協力して行う「信州りんごスイーツフェア」が毎年開催されています。長野市や中野市、安曇野市などのパティスリーが参加し、旬の信州りんごを使ったタルトやムース、コンフィチュールなどを期間限定で提供します。特徴的なのは、農家とパティシエが直接連携している点。糖度や酸味、果肉の硬さなど、スイーツに最適なりんごを選定することで、より香り高く、見た目にも美しい作品が生まれます。また、イベント期間中はSNS投稿キャンペーンやオンライン販売も行われ、県外のファンにも広がりを見せています。地域農業と菓子文化を結びつけた成功例といえるでしょう。
全国に広がるりんごスイーツ文化 ― 観光と地域活性の新たな形
りんごを使ったスイーツイベントは、今や全国各地で開催されています。北海道余市町の「余市りんごフェア」では、地元果樹園のりんごを使ったアップルパイやジェラートが人気を集め、山形県天童市では「天童りんごスイーツフェスタ」が市内カフェの共同企画として開催されます。さらに、東京都内でも地方とのコラボイベントが増加中で、アンテナショップや百貨店での「青森りんごフェア」「信州スイーツウィーク」などが定番化しています。これらの取り組みは、地方発のスイーツブランドを全国へと発信する役割を果たし、生産者と消費者をおいしさでつなぐ架け橋となっています。
【関連リンク】▶りんごを使った料理レシピ|朝・昼・夜・スイーツまで紹介
5. りんごと音楽・アートの融合イベント ― 五感で味わう新体験

りんごをテーマにしたイベントは、食や収穫体験にとどまらず、音楽やアートと融合した新しいスタイルへと広がっています。香り・音・光・映像を組み合わせた演出は、観光や地域文化の魅力をより多角的に伝える試みとして注目されています。
アップルミュージックフェス in 弘前 ― りんごの香りと音のコラボレーション
青森県弘前市では、りんごをテーマにした音楽イベント「アップルミュージックフェス in 弘前」が市内各地で開催されています。りんご園や公園を会場に、地元アーティストによるライブ演奏やシードル片手のカジュアルコンサートなど、音楽と食を同時に楽しめるのが特徴です。夜にはりんごのライトアップが行われ、幻想的な雰囲気の中でアコースティック演奏が響きます。地域のりんご農家が屋台を出店し、温かいアップルシナモンドリンクやアップルスープなどを提供。地元の人も観光客も一緒になって、りんごの香りに包まれながら秋の夜を満喫します。
アートと融合する「りんごの灯り展」 ― 光で表現する果実の美しさ
長野県や青森県では、近年「りんごの灯り展」や「アップルランタンナイト」といったアートイベントが増えています。りんごをモチーフにしたランプやキャンドルを展示し、夜のりんご園をやわらかい光で包む取り組みです。りんごの果皮や枝を使ったオブジェ、廃棄される果実を再利用したアート作品など、環境への配慮もテーマのひとつ。特に長野県中野市では、地元高校生が制作した「りんごの灯りアート」が展示され、SNS映えするスポットとして人気を集めています。アートを通して自然や農業の価値を再発見するきっかけにもなっています。
りんごでつながる体験型カルチャーイベントの広がり
りんごを題材にしたアートと音楽のイベントは、地域ブランディングの新しい形として全国に広がりを見せています。青森県板柳町では、りんご倉庫をリノベーションした「りんごの美術館」が開設され、収穫期にはライブペインティングや地元ミュージシャンの演奏が行われます。また、長野県安曇野市では、りんご畑を舞台にした写真展やクラフトマーケットを組み合わせた「アップルアートデイズ」が開催され、観光と芸術の融合による地域活性化が進んでいます。こうしたイベントは、りんごを食材としてだけでなく、文化や感性を育むシンボルとして位置づける動きでもあり、五感で味わう新たな体験型観光の形として注目されています。
6. りんご農家と出会う ― 作り手の想いを伝える交流イベント

りんごのイベントの中でも、注目を集めているのが農家との交流型イベントです。りんごがどのように育ち、どんな人の手で実っているのかを知る体験は、味わうだけでは得られない深い学びがあります。作り手の思いに触れることは、消費者にとっても「食への信頼」を育む大切な時間です。
農家トークセッションとりんごマルシェ
青森県板柳町や弘前市では、地元の生産者が登壇する「りんごトークセッション」や「りんごマルシェ」が定期的に開催されています。テーマは「持続可能な栽培」や「品種改良の裏側」など、普段は聞けないリアルな農業現場の話。実際に農家の方が自分の畑の写真を見せながら話す姿は、観光客だけでなく地元の若者にも刺激を与えています。会場では、収穫したてのりんごを使った焼き菓子やジュースの販売も行われ、農家と消費者の距離を縮める温かい雰囲気が広がります。農家の努力を知ることで、「同じりんごでも味わい方が変わる」と感じる人も多いようです。
若手農家の挑戦 ― 新しい栽培と発信のかたち
長野県や山形県では、若手農家が中心となってイベントを企画する動きも活発です。SNSを活用したオンラインりんご狩りや、規格外りんごを使ったアップルチップづくり体験など、従来の農業イベントとは一線を画す内容が人気を集めています。たとえば長野県飯綱町では、若手生産者グループ「iツナプロジェクト」が地域全体でりんごをPR。イベントで販売されるシードルやドライフルーツには、それぞれ生産者の名前とコメントが添えられており、「誰が育てたか」が分かる安心感が支持されています。こうした取り組みは、若い世代の就農意欲を高めるきっかけにもなっています。
農家の想いを伝える「食育」イベントの広がり
近年では、りんごを通じて食育を行うイベントも増えています。青森県黒石市や長野県中野市では、小学校と連携して「りんご授業」や「りんごの絵本読み聞かせ」を実施。子どもたちが実際に農園を訪れて収穫体験をし、生産者の話を聞くことで、食べ物の大切さや自然の循環を学ぶ機会となっています。さらに、都市部でも「青森りんごキッチン教室」「信州りんごフェア in 東京」などが開催され、産地の生産者が直接都会の消費者と交流する場が広がっています。こうしたイベントは、りんごの魅力だけでなく、地域や農業の未来をつなぐ架け橋としても重要な役割を果たしています。
7. シードルフェスティバル ― 発酵文化と地域の再発見

りんごの魅力をさらに広げる存在として注目されているのが「シードル(りんごのお酒)」です。近年、日本各地で開催されるシードルフェスティバルは、果樹産地の新たな文化イベントとして人気を集めています。りんご農家や醸造家、料理人が一堂に会し、発酵がつなぐ地域の輪を体感できる場となっています。
弘前シードルフェスティバル ― 日本のシードル文化の先駆け
青森県弘前市で毎年秋に開催される「弘前シードルフェスティバル」は、国産シードルブームの火付け役ともいえるイベントです。国内外のシードルが約100種類以上集まり、来場者はテイスティングを通して風味や製法の違いを楽しめます。弘前市は全国でも珍しいりんごとシードルのまちとして知られ、市内には「AOMORI CIDRE」や「タムラファーム」など複数の醸造所が点在。イベントでは、りんごの収穫から醸造までの過程を紹介するパネル展示や、シードルに合う地元食材のフードブースも登場します。地元シェフが手がけるシードルペアリングメニューは特に人気で、青森りんごの個性豊かな味わいを再発見できると評判です。
信州シードルコレクション ― りんご王国が育む多様なテロワール
長野県では「信州シードルコレクション」が開催され、県内外の醸造所が一堂に集まります。飯綱町、小諸市、安曇野市など、標高や気候の違いによって生まれる個性豊かなシードルを味わえるのが特徴です。中でも「サンサンワイナリー」や「マルカメ醸造所」のシードルは、香りの良さと繊細な泡立ちが高く評価されています。イベントでは、生産者がステージに立ち、りんごの栽培方法や発酵の工夫を直接語るトークセッションも実施。農業と発酵学の知見が融合した内容で、シードルを文化として楽しむという意識が広がっています。また、近年は環境に配慮した「オーガニックシードル」も注目を集め、持続可能な生産の取り組みとして注目されています。
地域をつなぐ発酵ツーリズムの広がり
シードルイベントの魅力は、飲むだけでなく地域を巡る楽しさにもあります。青森や長野では、シードルを軸にした観光ルート「シードルツーリズム」が整備され、農園・醸造所・カフェを巡る体験が人気です。青森県黒石市では「りんごとシードルの里フェア」、長野県飯綱町では「いいづなシードルガーデン」が開かれ、試飲だけでなくボトルデザイン体験や醸造見学も行われています。こうした取り組みは、地域経済の活性化に加え、農業・観光・食文化を横断的に結びつける役割を果たしています。りんごが食べる果物から地域を象徴する文化資源へと進化する――シードルフェスティバルはその変化を象徴する存在といえるでしょう。
8. りんごでつながる家族イベント ― 親子で学び楽しむ企画

りんごをテーマにしたイベントの中でも、家族で楽しめる「体験型企画」は特に人気があります。小さな子どもから大人までが一緒に参加できる活動を通して、りんごの魅力を学びながら食と自然のつながりを感じられることが魅力です。観光地や都市部でも年々増えており、食育や地域体験の場として注目されています。
親子で楽しむりんご収穫体験と加工教室
秋の収穫シーズンには、全国各地の観光農園で親子向けの「りんご収穫体験」や「りんごジュースづくり教室」が開催されています。青森県弘前市の「弘前りんご公園」では、ガイドと一緒に園内を巡りながら、収穫のコツや品種の違いを学べるプログラムが人気です。自分で収穫したりんごをその場で試食し、搾汁体験を通してジュースに加工するまでを学ぶことで、食べ物が食卓に届くまでの流れを理解できます。長野県中野市や飯綱町でも同様の体験があり、親子でりんごの香りや手ざわりを感じながら、自然の恵みを実感できる内容となっています。
工作・スイーツづくり・りんごアート体験
収穫だけでなく、創作を通じてりんごの魅力を学べるイベントも増えています。長野県安曇野市や青森県黒石市では、りんごの枝や木箱を使った「クラフト体験」、りんごをモチーフにした「スイーツデコ教室」などが開催されています。小さな子どもでも楽しめるよう、色塗りやシール貼り、りんごスタンプなどのプログラムが用意されており、親子で一緒に作品を作る時間が人気です。さらに、りんごを使ったスイーツづくり体験も好評で、アップルパイや焼きりんごを親子で作りながら食育を学ぶことができます。素材を生かした香りや焼き色を体験することで、子どもたちの五感が刺激されるのも魅力です。
都市部にも広がるりんごの学びイベント
りんごイベントは、近年では都市部にも広がりを見せています。東京・大阪・名古屋などでは、青森県や長野県の自治体が主催する「親子りんご教室」や「りんごフェア」が商業施設やアンテナショップで行われています。たとえば、東京・有楽町の「青森県産品プラザ」では、りんご農家が来場して講話を行う親子向けワークショップを実施。りんごの品種の見分け方や保存方法、皮ごとの栄養などをわかりやすく学べます。地方に行かなくてもりんごの文化に触れられる機会が増えており、これをきっかけに実際の産地へ旅行する家族も多いようです。りんごが「食べる」だけでなく、「学ぶ・体験する」果物として親しまれるようになった背景には、こうした取り組みの積み重ねがあります。
9. オンライン・デジタル時代のりんごイベント ― 新たな発信の形

コロナ禍以降、りんごイベントにもデジタル化の波が広がりました。現地での参加が難しい人々に向けて、オンライン収穫体験やライブ配信型マルシェなど、画面越しでもりんごの季節を感じられる取り組みが増えています。地域の魅力を全国へ発信するための新しいスタイルとして、オンラインイベントは定着しつつあります。
オンライン収穫祭とライブ中継による産地体験
青森県や長野県の自治体では、オンラインで楽しめる「りんご収穫祭」や「産地ライブ中継」が年々拡大しています。青森県弘前市では、農家と中継をつなぎ、りんごのもぎ方や選び方をリアルタイムで紹介。参加者は事前に申し込むと、実際に農家が収穫したりんごが自宅に届き、画面越しに味見をしながら交流を楽しめます。長野県飯綱町でも、地元生産者と視聴者が直接対話できる「オンラインりんご狩りツアー」が人気。農園の風景や作業風景をドローン映像で配信し、臨場感ある体験を提供しています。こうした試みは、遠方からでも産地の空気を感じられる新しい形の観光として注目されています。
SNS発信とフォトコンテスト ― 若年層の関心を高める仕掛け
オンラインイベントでは、SNSを活用した参加型企画も活発です。青森県板柳町の「りんごまるかじりまつり」では、公式Instagramで#まるかじりフォト投稿キャンペーンを実施し、全国から美しいりんご写真が集まりました。長野県中野市では、「信州りんごウィーク」と題して、消費者が自宅で撮影したりんごスイーツ写真を募集。優秀作品は地元カフェとのコラボメニューとして商品化されました。SNSを通じた発信は、若い世代が自然や農業に関心を持つきっかけになり、オンライン上でも地域のファンづくりが進んでいます。また、動画投稿やライブ配信などを通して、農家自身が自分の畑を紹介するケースも増えており、情報発信の担い手が多様化しています。
デジタルとリアルをつなぐハイブリッドイベントの可能性
近年では、オンラインと現地イベントを組み合わせたハイブリッド型りんごイベントも増えています。たとえば、青森県黒石市では「オンライン×現地同時開催フェス」として、現地の農園ライブ映像を会場スクリーンに投影し、全国の参加者と同時に乾杯を楽しむ取り組みを実施。東京・大阪など都市部でも、青森県や長野県のアンテナショップが中心となり、現地農家との中継トークや限定商品の販売会が行われています。こうした形は、移動が制限されても地域とのつながりを維持できる新しい観光の形として定着しつつあります。デジタル技術を活用することで、りんごイベントは「遠くても参加できる」ものへと進化し、地域のファンを全国に広げています。
10. 未来へ実るりんごイベント ― 地域・人・文化をつなぐ架け橋

りんごイベントは今、単なる観光行事から、地域の未来を支える文化的資産へと進化しています。気候変動や後継者不足といった課題を抱えるなかで、地域が一体となって「りんごを守り、伝える」ための新しい試みが各地で始まっています。りんごを中心に、人と人、地域と都市をつなぐ動きが広がっています。
若手農家・学生・企業がつながる新しいプロジェクト
青森県や長野県では、若手農家や大学生、地域企業が連携して新しいりんごイベントを企画する取り組みが増えています。たとえば、青森県板柳町の「りんご未来会議」では、地元高校と農協、食品メーカーが協力し、次世代が考えるりんごの楽しみ方をテーマにシンポジウムを開催。りんごの廃棄部分を使ったクラフト製品の開発や、エシカル消費を意識した販売方法など、若い感性から生まれたアイデアが注目されています。長野県飯綱町では、学生と農家が協働でりんごフェスを運営し、来場者との交流を通じて農業への関心を高める試みも。こうした動きは、地域に新しい担い手を呼び込む原動力になっています。
環境にやさしいりんごイベントの実現へ
近年、りんごイベントではサステナビリティ(持続可能性)を重視した取り組みも広がっています。青森県弘前市では、イベントの屋台で使用する容器をバイオマス素材に切り替え、食品ロス削減を目的とした「もったいない市」を併設。規格外りんごの販売や、加工品として再利用するワークショップも行われています。長野県中野市の「信州エコりんごフェスタ」では、太陽光発電を活用した電源供給や、地元の木材を利用した装飾を採用。りんごを自然と共に生きる果実して発信する姿勢が、多くの来場者に共感を呼んでいます。こうした取り組みは、地域全体の環境意識を高め、持続可能な観光・農業のモデルケースとして全国に広がりを見せています。
地域文化としての「りんご」を未来へつなぐ
りんごイベントの本質は、単に果物を楽しむことではなく、「地域の歴史・文化・人の想いを共有する場」にあります。青森・長野・山形といった産地では、100年以上続くりんご栽培の歴史を次世代に伝える活動も活発です。弘前市では、りんごを題材にした演劇や写真展が開催され、地域の物語としてりんごの存在が再認識されています。また、都市部のアンテナショップでは、産地と連携した常設フェアを通じて、年間を通してりんご文化を発信。こうした活動が「りんごを通じて地域を知る」きっかけとなり、観光や教育、ビジネスの分野へと発展しています。りんごイベントは今後も、地域を超えて人々を結びつける文化の架け橋として成熟していくでしょう。
🍊 さまざまな果物について、栄養・レシピ・豆知識をまとめています。
ぜひ気になるフルーツカテゴリから、お好みのテーマを見つけてください!